みなさん、こんにちは!ゆっぽです。
今回のテーマはタイトルにもある通り、ズバリ「チーズ」です。
日本においても最近では、チーズケーキやチーズフォンデュなど、チーズを使った様々な料理が流行っていますが、実は海外でもチーズは爆発的な人気を集めているのをご存知でしょうか?

筆者は最近バスクチーズケーキとやらがすごい気になっているよ!
現地のスーパーマーケットではチーズ専門のコーナーが併設されていたり、街中でもチーズ専門店をよく見かけるくらい、チーズは海外の人々にとっても欠かせない食材の一つとして万人に愛されています。
そんなチーズですが、世界にはなんと1000種類以上ものチーズがあると言われているのだそうです。
日本ではスライスチーズやベビーチーズなどのいわゆる「プロセスチーズ」が人気ですが、一般的なチーズは生乳から作られ、これらは「ナチュラルチーズ」としてそこからまたさらに「フレッシュタイプ」や「セミハードタイプ」など大まかに分けて7つの種類に分類されます。
そこで今回は、筆者が海外滞在中に出会ったお気に入りのナチュラルチーズを5つ、ご紹介したいと思います。
日本ではあまり馴染みのないチーズもありますので、この記事を読むことでみなさんに少しでもチーズの奥深さについてご理解頂ければ幸いです。
それではさっそく、どうぞ!
Feta cheese(フェタチーズ)

フェタチーズ (φέτα, feta) は、羊あるいは山羊の乳からつくられるチーズのひとつ。フェタとも。
参考:wikipedia
ギリシャの代表的なチーズである。白色のねっとりした塊状の外観で、食塩水中で熟成させるために強い塩味がある。そのままメゼの一品として、またサラダやサガナキ、おかずパイの素材として食べる。
はじめにご紹介するのは、ギリシャ原産のフレッシュチーズ、フェタチーズです。現存する世界最古のチーズとも言われているこちらのチーズは、羊や山羊の乳からつくられており、古代ギリシャの時代から食べられてきたとても歴史の深いチーズです。
見た目はお豆腐にそっくりで、食感も身が引き締まっており、口の中でホロホロと崩れていくような感覚です。サッパリとした見た目とは裏腹に、味はしっかりとした塩気があり、ほのかな酸味も感じられます。
そのまま食べても塩気を感じることが出来るので美味しく味わうことができますが、本場のギリシャではよく、サラダの具材に使われたり、ピタと呼ばれるパイ料理の具材として使用されることが多いです。
スーパーマーケットでは真空パックに包装されたフェタチーズをよく見かけることがありますが、前述したようにフレッシュタイプのチーズのため、出来れば一週間程度で食べきるのが理想とされています。
栄養も豊富でダイエットにも最適なチーズになっていますので、女性の間では特に人気の高い、ヘルシーなチーズと言うことが出来るでしょう。
Gouda cheese(ゴーダチーズ)

ゴーダチーズは、エダムチーズと並ぶオランダの代表的なチーズ。オランダでのチーズ生産量の60 %を占める。
参考:wikipedia
ロッテルダム近郊の町、ゴーダで作られたことからこの名前がついた。正確な起源は不明だが12世紀頃にまで溯るとされることが多い。
続いてご紹介するのは、チーズ大国オランダの中でも生産量の半分以上を占める代表的なチーズ、ゴーダチーズです。
こちらはいわゆる「セミハードタイプ」のナチュラルチーズにあてはまり、日本のプロセスチーズの多くがこのゴーダチーズを原料としていることも知識として押さえておきたいところです。
弾力がありマイルドでクセがないのが特徴で、熟成すると色合いは濃くなり、旨味と甘みが増していきます。
そのマイルドさの秘密は、カードウォッシングと呼ばれる製法でカード(ミルクに乳酸菌と凝乳酵素を加えミルクプリン状に固まったものから、ホエイを抜いたもの)を湯で洗い、乳糖を減らし雑菌対策をして作られていることにあり、チーズ初心者にも食べやすい味わいに仕上がっています。
ワインのおつまみとしてそのまま食べてももちろん美味しいですし、パスタやグラタンと合わせたり、トーストに乗せて焼いてみても非常に美味しいです。
このようにクセがなく食べやすいチーズはどんな料理とも相性が良いので、食卓を彩る万能アイテムとしても重宝できるチーズと言えそうです。
Halloumi cheese(ハロウミチーズ)

ハルーミ、ハロウミ (Halloumi)は、キプロス料理の一種で、ヤギ乳と羊乳の混合物から作られるセミハードタイプの非熟成塩漬けチーズである。
参考:wikipedia
原料に牛乳が用いられることもある。融点が高く、フライやグリルに適している。ハルーミの製造にはレンネットが用いられ、酸や酸産生細菌は用いられない。
3番目にご紹介するのは地中海東部キプロス島産のちょっと変わったセミハードタイプのチーズ、ハロウミチーズです。
筆者がこのチーズに初めて出会ったのはニュージーランドでワーホリ生活をしていた時だったのですが、初めて食べた瞬間はこれがチーズだとは気付きませんでした。というのもこのチーズ、鶏のささみのような見た目をしており、融点が高いため揚げても焼いても簡単には融けないのです。
食感も非常に独特で、食べると弾力があり、モキュモキュと音がします。こちらもフェタチーズ同様、しっかりとした塩気が感じられますが、同時にミルクの甘さも楽しむことができ、とてもまろやかな味わいに仕上がっています。
調理法としては、先ほどもお伝えしたように融けにくいチーズのため、グリルで焼いたり、衣をつけて揚げたりするとまた違ったチーズの楽しみ方が出来て非常に新鮮です。
こんがりと焼き目が付いたハロウミチーズはまるで焼きたてのお餅のような仕上がりになり、アツアツでとても美味しいです。
また、ハンバーガーに挟んでも大変美味ですので、近年ではベジタリアンの間でも注目度が高まっているチーズの一つでもあります。

そのうち日本でもハロウミチーズブームが来ると筆者は予想しているよ♪
Cream cheese(クリームチーズ)

クリームチーズは、牛乳とクリームから作られる非熟成の軟質チーズである。穏やかな酸味とバターのような滑らかな組織が特徴である。
参考:wikipedia
アメリカ食品医薬品局(FDA)では、乳脂肪分33%以上、水分55%以下、pH4.4-4.9のものをクリームチーズと定義している。
4番目にご紹介するのは日本でもお馴染みのフレッシュタイプチーズ、クリームチーズです。滑らかな口当たりと爽やかな酸味が特徴的なこちらのチーズは、みなさんもご存知アメリカのフィラデルフィアにてその歴史をスタートさせたと言われています。
近年では家庭でも簡単に作ることができるため、多くのアレンジレシピも開発されているこちらのクリームチーズですが、その用途も実に多岐にわたります。
パンやベーグル、クラッカーに塗って食べるのはもちろんのこと、本場アメリカではマッシュポテトに入れて混ぜ合わせたり、その他にもサラダのトッピングや、スモークサーモンの付け合わせとして用いられることもあるそうです。
また、お菓子作りにおいてもクリームチーズは欠かせない材料でもあります。美味しいチーズケーキやキャロットケーキには、必ずと言っていいほど良質なクリームチーズが使われています。
筆者はベタですが写真のようなサーモンとクリームチーズのベーグルが大好きで、海外のカフェでもよく注文して食べていました。また、シンプルに色々なスナックにディップして食べるのもとてもやみつきになる美味しさがあります。
ホームパーティーなどでは大活躍するチーズに間違いないので、友人や家族と食卓を囲む際にはぜひ常備しておきたいチーズです。
Gruyere cheese(グリュイエールチーズ)

グリュイエールチーズ(Gruyère)はスイス・グリュイエール (英語版)地方原産のチーズの一種。牛の生乳を熱して原料とし、黄色からオレンジ色の外皮に包まれた、やや舌に結晶を感じる密に詰まったチーズで、塊の大きさは直径55cm~65cm、高さ9.5cm~12cm、重さは25kg~40kgである。無腔質のグリュイエールの呼び名はスイス産のものに限られている。
参考:wikipedia
最後にご紹介するのは、エメンタールチーズと共に、スイスの2大有名チーズと言われているうちの一つ、グリュイエールチーズです。
無殺菌の牛乳から造られるハードタイプのチーズであるこちらのグリュイエールチーズは、マイルドな口当たりと、旨味が凝縮された深い味わいが特徴となっています。
また、こちらのチーズは熟成期間や作り方によって種類が分けられており、熟成期間が長くなるにつれて「レゼルヴ」、「ダルパージュ」と呼ばれスタンダードなグリュイエールチーズとは区別されます。
熟成期間が短いものは乳白色をしており、生乳の甘味が堪能できるのに対して、熟成が進むにつれて色が濃くなり、香りも強くなります。
こちらのチーズも様々な料理のレシピに活用されており、代表的なものを挙げるとキッシュやクロックムッシュ、グラタン、オニオングラタンスープなどに用いられています。
また、その円形で大きいサイズという特性を活かして、ラクレット用のチーズとしても使用される場面が多くあります。トロトロに溶けたチーズが滝のように流れ落ちる様は、見ているだけでも引き込まれてしまうこと間違いなしです。

まさにチーズのナイアガラやぁ~♪
まとめ
いかがでしたでしょうか?日本のスーパーマーケットではあまり見かけないようなチーズもあったりして、意外と驚いたという方も多いのではないかと思います。筆者も海外のチーズ専門店を覗いたときは、そのあまりの種類の多さに圧倒されてしまいました。
これほどまでに人々の日常生活にすっかり浸透しつつあるチーズ文化ですが、今後もさらにその勢いを加速させていくことが期待されています。みなさんもこれを機に、一足先にこの来たるべきチーズブームの波に乗ってみてはいかがでしょうか?
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ではまた、See you soon!
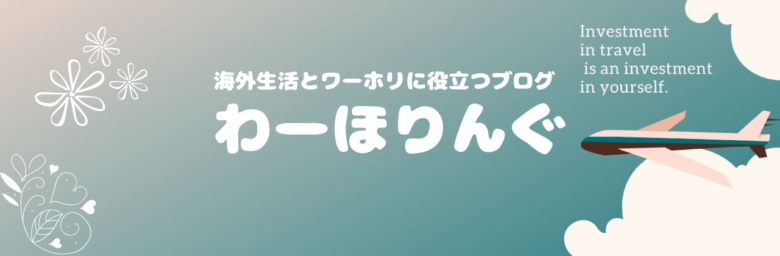
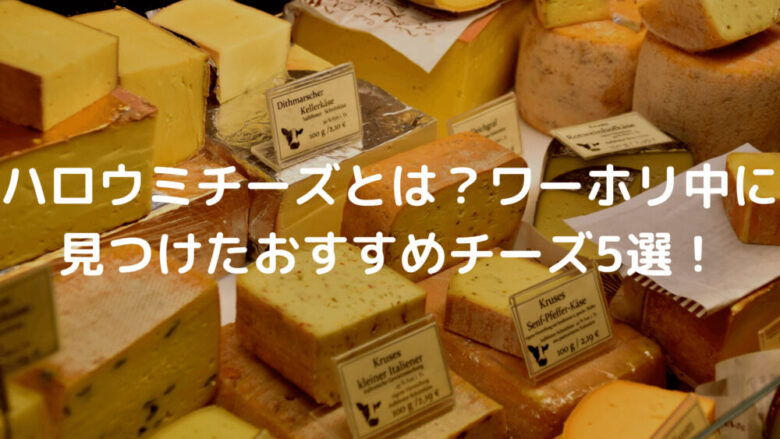

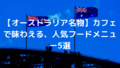
コメント